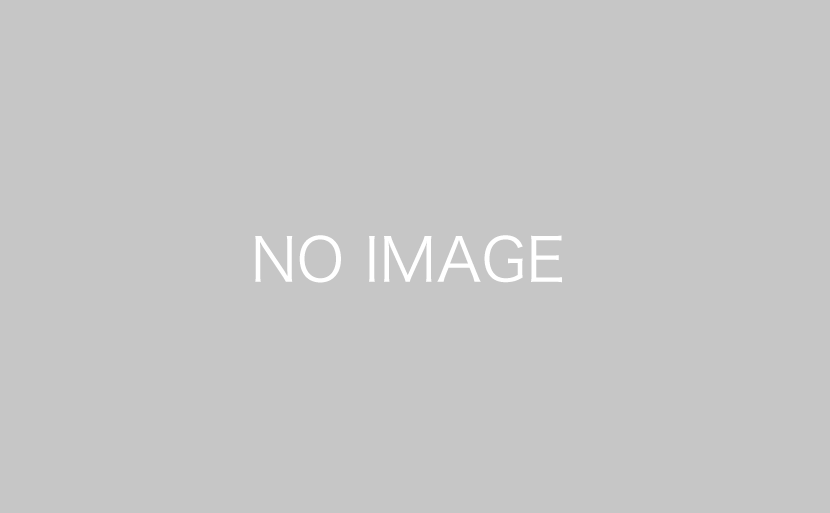溶連菌の症状・感染方法
溶連菌ってなんですか?
こたえ. バイ菌の一種でさまざまな症状を引き起こします。
溶連菌感染症は「溶血性連鎖球菌」というバイ菌の感染によって引き起こされる病気です。「溶血性連鎖球菌」にはいくつかの種類が存在しますが、特に感染症を起こす頻度が高く、一般によく知られているのが「A群溶血性連鎖球菌」です。溶連菌感染症というのは、この「A群溶血性連鎖球菌」によるものと考えてください。
「A群溶血性連鎖球菌」は、上気道炎、咽頭炎、皮膚や皮下組織などの感染症の原因菌としてよくみられるバイ菌の一つで、いろいろな症状を引き起こすことで知られています。
日常よくみられる病気として、
- 急性咽頭炎(のどの炎症)
- 膿痂疹(のうかしん:皮膚の炎症)
- 蜂窩織炎(ほうかしきえん:皮膚の下の組織の炎症)
- 猩紅熱(しょうこうねつ:全身の皮膚症状、関節の炎症、手足の痛みなどが出る病気)
などが挙げられます。これら以外にも、
- 中耳炎、肺炎、化膿性関節炎、骨髄炎(骨の中の炎症)
- 髄膜炎(脳やせき髄の周りに起こる炎症)
なども引き起こす場合があります。また、菌が直接悪さをするのではなく、感染した人の免疫を介して、
- リウマチ熱(炎症が関節、心臓、血管、神経等におこる病気)
- 溶連菌感染後急性糸球体腎炎
なども起こすことが知られています。
どんな人が感染しやすいの?
こたえ. 学童期のお子さまが最も感染しやすいです。
学校(幼稚園・保育園)は行っていいの?
こたえ. 多くの地域では出席停止として扱われます。
治療開始から24時間以上経過し、全身状態がよければ登校(登園)許可証を発行しています。学校保健安全法施行規則第18条において、学校で流行が起こった場合、必要に応じ校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として出席停止措置をとれる疾患です。
どうやって感染するの?
こたえ. 唾液などが口に入ることで感染する、飛沫感染(ひまつかんせん)です。
多くのお子さまが集団生活を行う保育園、幼稚園、学校はもちろんのこと、ご家庭内でも感染することが多いです。健康な人でも約3割程度の人が溶連菌を保菌しているという報告もありますが、健康保菌者からの感染はまれであると言われています。
診察では、喉の検査で溶連菌がいる=溶連菌感染症ではなく、その他の症状も含めて総合的に診断します。
感染後どのくらいで、どんな症状がでるの?
こたえ. 溶連菌の潜伏期は2〜5日程度です。
潜伏期に感染性があるかどうかは分かりません。熱、喉の痛み、発疹などが主な症状です。発熱、全身倦怠感、咽頭痛によって発症することが多いです。
診察上、喉には点状の赤い出血を認め、苺のつぶつぶの様な舌がみられることがあります。合併症として、肺炎、髄膜炎、敗血症、あるいはリウマチ熱、急性糸球体腎炎などが挙げられます。ただし、3歳以下の乳幼児や成人では、典型的な症状があまり出ないことが特徴として挙げられます。
溶連菌の診断、治療のしかた
どうやって溶連菌感染症を診断するの?
こたえ. 溶連菌の検査方法には、「迅速検査」「培養検査」「抗体検査」の3つの方法があります。
これらの検査結果と症状を組み合わせて総合的に診断します。
診断方法はいくつかあります。以下に確定診断の方法を挙げます。
| 迅速診断 | 喉をこすって溶連菌がいるかどうか、菌の蛋白質との反応から診断する方法です病院内で綿棒で喉をぬぐってすぐにわかる検査です |
|---|---|
| 培養検査 | 喉の擦過物を培養し、菌がいるかどうかを目で確認する方法です。専門の検査会社に提出するため、時間がかかります。 |
| 抗体検査 | 血液の抗体の上昇があるかどうかを確認する方法です。専門の検査会社に提出するため、時間がかかります。 |
続いて、それぞれの検査について具体的にご説明します。
①迅速診断
迅速診断キットは、他の種類のA群連鎖球菌でも陽性結果が出たり、菌数が少ない場合には陰性結果が出ることがあります。また、ただ咽頭に保菌しているだけでも陽性に出ることがあるため、症状と照らし合わせながら判断する必要があります。
②培養検査
受診前(検査前)に抗生剤を服用していると、溶連菌感染症であっても溶連菌が培養検査で検出されないことが多いです(抗生剤を内服した6〜12時間後には、咽頭培養を行っても培地で溶連菌が増殖しなくなっています)。A群溶連菌は健康な人にも咽頭や鼻に保菌されていることあります。
咽頭培養で、A群溶連菌が検出されても、特に菌量が少ない場合、症状(発熱など)の原因微生物でないこともあります。1でも説明しましたが、健康であっても喉に溶連菌を保菌している学童が15〜30%程度いるという報告もありますので、症状と照らし合わせながら判断する必要があります。
③血液の抗体(ASO、ASK)の上昇があるかを確認する方法
溶連菌に感染すると、体の中にある特定のたんぱく質(ASOとASKという)が上昇します。これらのたんぱく質を測定することで、感染があるかどうかを判断します。
ASOなどが上昇するには、早くても感染から1週間後あたりであり、通常は2週間程度と言われています。そのため、急性期の診断にはあまり有用ではありません。ASOなどは、溶連菌感染3〜5週間後(約4週後)にピークに達します。2〜3か月で正常値に回復することが多いようです。
症状と上記のそれぞれの検査の特徴を考慮し、それぞれを組み合わせながら確定診断をしていきます。
どのように治療・予防するの?
こたえ. 溶連菌の治療には抗生剤の内服が必要です。
抗生剤は決められた回数、日数で確実に内服してください。
治療にはペニシリン系の抗生物質(サワシリン、ワイドシリン、パセトシンなど)を使用します。ペニシリン系の抗生物質にアレルギーがある場合にはエリスロマイシン(エリスロシンなど)、クラリスロマイシン(クラリス、クラリシッドなど)を内服します。
また、セフェム系の抗生剤(メイアクト、フロモックスなど)などを使用することもあります。リウマチ熱、急性糸球体腎炎など、非化膿性の合併症予防のために、少なくともペニシリン系であれば10日間、セフェム系であれば7日間は確実に内服することが必要です。
溶連菌の予防方法としては、患者との濃厚接触をさけることが最も重要であり、うがいや手洗いといった一般的な予防方法を日頃からしっかり行うことも大切です。
感染後に尿検査は必要ないの?
こたえ. 溶連菌感染後の急性糸球体腎炎の早期発見のための尿検査は必要ありません。
「溶連菌感染後に尿検査をしなくてもいいのでしょうか?」と患者さまからご質問いただくことが多々あります。溶連菌に感染した後に体の中で免疫反応が起き、その結果として腎臓に影響が出て「溶連菌感染後急性糸球体腎炎」という病気が発症することがあります。この腎炎では、「おしっこの量が減る、おしっこが茶色くなる、顔や手足がむくむ」といった症状が出ます。
結論から申し上げると、溶連菌に感染した後に発症する「溶連菌感染後急性糸球体腎炎」を早期に発見するための尿検査はあまり意味がありません。なぜなら、治療が必要な「溶連菌感染後急性糸球体腎炎」は、症状として明らかな場合がほとんどだからです。
「おしっこの量が減る、おしっこが茶色くなる、顔や手足がむくむ」といった症状が出ているかをしっかりと観察することが重要で、症状が出ていれば医療機関を受診し、診断・治療を受けることが必要です。
キャップスクリニックでは、医師・看護師・医療クラークの皆様を募集しています!
キャップスクリニックは首都圏を中心に365日診療を実施しています。

①365年中無休で朝9時~夜21時まで診療(一部クリニック除く)
キャップスクリニックでは、「標準的な治療」を365日受けることができる「治療提供拠点」を維持し、普及することに努めています。
日々お忙しい中でも安心してご受診いただけるよう、朝9時~21時まで開院しております(一部クリニックを除く)。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆なども休まず診療しておりますので、いつでもご来院ください。
②ご家族の皆様もご一緒に!
小児科でも、お子さまとご一緒にご家族の皆様も診察・予防接種等をお受けいただけます(受診される方全員のご予約・ネット問診をお済ませください)。
※ご症状によっては内科受診をお勧めさせて頂く場合がございます。
また、当院は24時間ネット予約受付システムを運営しており、いつでもご予約および事前問診が可能です。ご家族の皆様で同じお時間にまとめてご予約していただくことも可能となっております。
ご家族の皆様が同じ時間に予約する方法
③1枚の診察券で全クリニックをご受診いただけます
キャップスクリニックは首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)を中心に小児科・内科のクリニックを運営しており、全クリニック共通の診察券でご受診いただけます。
④予防接種、各種健診を毎日実施しています
一般的に、予防接種は乳児健診などは曜日が限定されているクリニックが多い中、キャップスクリニックでは予防接種・健診を毎日実施しています(事前予約が必須)。
原則、当院は朝から21時まで診療しておりますので、お忙しい中でもご都合のよいタイミングでご来院いただけます。