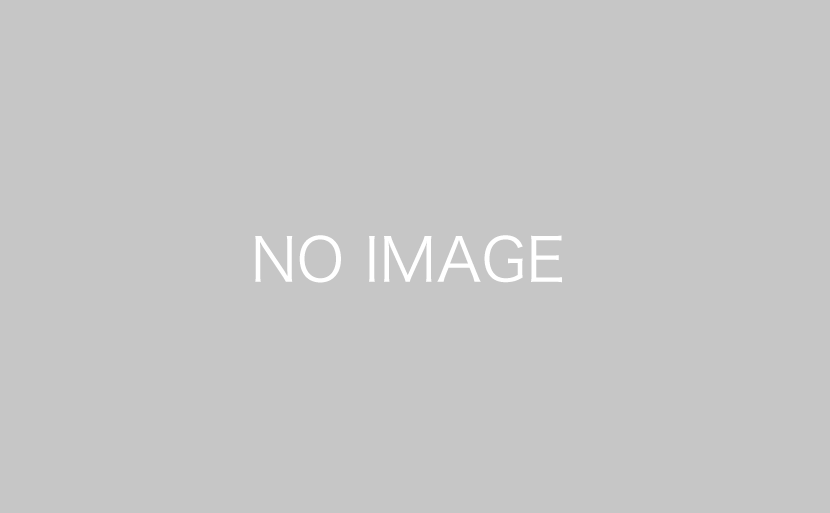RSウイルスとは?
風邪を引き起こすウイルス
RSウイルスは、正式には「Respiratory syncytial virus(レスピラトリーシンシチアルウイルス:RSウイルス)と言い、感染すると年齢を問わず、風邪などの症状を引き起こすウイルスです。 ちなみに、風邪の80~90%はウイルス感染が原因です。
小さなお子さまは重篤化の可能性もある
新生児、乳幼児期(特に1歳未満)において非常に重篤な症状を引き起こすことがあるため、注意が必要なウイルスでもあります。
特に、出生体重が軽く小さく生まれたお子さまや、心臓や肺の基礎疾患といった免疫不全がある場合には、重症化のリスクが高いことが知られています。2歳以上のお子さまは軽い「鼻風邪」で終わることが多いですが、1歳未満、特に6か月未満の赤ちゃんは重症化することがありますので注意が必要です。
よく「保育園・幼稚園でRSウイルスが流行っているから心配」と受診される方がいらっしゃいます。まずは、RSウイルスに感染して重症化するリスクのある年齢かどうかを判断する必要があります。
1歳を越えていれば多くの場合には重症化するリスクは軽減していきます。1歳になるまでに50〜70%のお子さまがRSウイルスに感染します(2歳までにほぼ全員1回は感染します)。そして、何回も感染するのが特徴です。RSウイルスはどこにでもいる風邪のウイルスで、大人でも何回も感染し、年長児や大人に感染すると鼻の症状だけ引き起こすようなウイルスなのです。
流行期・主な症状
晩秋〜冬〜早春にかけて流行しますが、その年によって流行の時期や程度は異なります。
RSウイルスに感染するといわゆる風邪の症状が出ます。感染者の咳、鼻水を浴びたり、触ったりすることで感染(飛沫、接触感染)し、4〜5日の潜伏期を経て、咳、鼻水、発熱などが症状として現れます。発症前の4〜5日(潜伏期間中)から発症後10〜14日間ほどでウイルスを排出しますが、時には1か月程度も排出にかかる場合もあります。
注意しなければいけない症状は以下のとおりです。
- 息を吐くときに「ヒュー、ヒュー」「ゼー、ゼー」と音がする(喘鳴:ぜんめいといいます)
- 顔色や唇の色が悪い
- 胸がペコペコとへこむような呼吸をする
- 呼吸が速く、呼吸の回数が極端に増えている
このような場合には、RSウイルスによって引き起こされる重症な疾患である、肺炎、気管支炎、細気管支炎などを発症している可能性があります。肺炎、気管支炎、細気管支炎を発症した時には、場合によっては酸素投与、点滴などの処置が必要であり、入院し経過観察が必要な場合もありますので、ご注意ください。
生後3か月未満の赤ちゃんでは、典型的な症状が出ない場合もあり、哺乳不良、活気不良、無呼吸発作、チアノーゼ(皮膚の色が紫色になる状態)などの症状を認めることもあります。無呼吸発作は命にかかわる重篤な症状ですので、細心の注意が必要な症状です。
RSウイルスに感染したら?
RSウイルス感染症の検査
鼻粘膜のぬぐい液を使用して、15分程度の迅速診断が可能です。鼻の穴に細い綿棒を入れて検査します。とはいえ、RSウイルスの検査は、RSウイルス感染症が疑われる全ての患者さまに行う検査ではありません。
生後1〜2か月の赤ちゃんでRSウイルス感染症が疑われる場合、経過中に無呼吸発作などの重症な症状を呈する危険があるため、重症化する経過を予想し、入院し経過観察が必要かどうかを判断するために積極的に検査を行います。
また、その他入院が必要な程度の症状を呈す場合も検査を行います。1歳以上のお子さまに関しては重症化のリスクは低く、以下にご説明する通り特別の治療法もないことから、治療方針を決定する上で、RSウイルス迅速検査で感染を特定する必要性はほとんどありません。
1歳以上のお子さまでどうしても検査を強くご希望される場合、保険診療内での検査は対応出来かねますため、診察・検査含め自費診療での対応となりますこと、予めご了承ください。
RSウイルスに効く薬は?
RSウイルス自体に効果のある抗ウイルス薬はありませんので、症状に合わせて対症療法を行うのが基本的な治療です。
去痰薬、解熱薬、理学療法(痰を出しやすくしたりする体位を取らせたり、吸入をしたりするもの)を行います。ご自身の免疫力で良くなるように体力の回復を助ける薬を内服したり、吸入などの処置で呼吸状態を改善してあげることが必要です。
現在、重症化のリスクの高いお子さまに対して、重症化の抑制薬(抗RSウイルスモノクローナル抗体:商品名シナジス)を予防投与することが認められていますが、対象となっているのは在胎36週未満の早産のお子さま、および慢性肺疾患や先天性心疾患をお持ちの乳幼児のお子さまです。
RSウイルスの基本的な予防方法は、日頃の手洗いうがいや、マスク着用になります。
さいごに
保育園、幼稚園でRSウイルスが流行っていても、お子さまの年齢と重症化するリスク(小さく生まれた、早産、肺や心臓の疾患がある)があるのかをしっかりと把握してください。
うちの子は重症化するような年齢(1歳未満:特に生後6か月未満)なのか、重症化するリスク(心臓、肺に疾患がある、早産、小さく生まれた)があるのかをしっかりと考えて、慌てずに医療機関を受診しましょう。
キャップスクリニックの特長

①365年中無休で朝9時~夜21時まで診療(一部クリニック除く)
キャップスクリニックでは、「標準的な治療」を365日受けることができる「治療提供拠点」を維持し、普及することに努めています。
日々お忙しい中でも安心してご受診いただけるよう、朝9時~21時まで開院しております(一部クリニックを除く)。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆なども休まず診療しておりますので、いつでもご来院ください。
②ご家族の皆さまもご一緒に!
小児科でも、お子さまとご一緒にご家族の皆様も診察・予防接種等をお受けいただけます(受診される方全員のご予約・ネット問診をお済ませください)。
※ご症状によっては内科受診をお勧めさせて頂く場合がございます。
また、当院は24時間ネット予約受付システムを運営しており、いつでもご予約および事前問診が可能です。ご家族の皆様で同じお時間にまとめてご予約していただくことも可能となっております。
ご家族の皆様が同じ時間に予約する方法
③1枚の診察券で全クリニックをご受診いただけます
複数クリニックに展開しているキャップスクリニックを、共通の診察券でご受診いただけます。
④予防接種、各種健診を毎日実施しています
一般的に、予防接種は乳児健診などは曜日が限定されているクリニックが多い中、キャップスクリニックでは予防接種・健診を毎日実施しています(事前予約が必須)。
原則、当院は朝から21時まで診療しておりますので、お忙しい中でもご都合のよいタイミングでご来院いただけます。